自分の人生のハンドルを自分で持つ覚悟ができた時、いつも始まる物語
21.06.05 INTERVIEW
父は鹿児島の高校を卒業して、川崎に出てきた。大きな化学プラントの制御保守の仕事。言葉は少々粗くて、いつも何かに吠えていた印象がある。あと、双子の妹と母。日本中のどこにでもあるような社宅に家族4人で住んでいた。

実直で、社交的な父。仕事も熱心に頑張っていた。ただ「高卒」というだけで、満足な給料にならない。不満もあっただろう。物心ついた時には、当然のように「お前は大学に行け。」と言われていたし、自分もそのつもりでいた。
小学校3年生からは塾に通っていた。勉強は好きだったし、得意だった。そのわりにスポーツもできたので、活発な少年だったと思う。「長」がつくものはたいていやった。責任感をもってリーダーシップを発揮する。そういうポジションは嫌いじゃなかった。
それでも塾では、毎週テストがあり、中の上クラスでいることがやっとだった。学校では勉強ができる方でも、‟上には上がいる ”ことはこの頃から知っていた。
5年生の時に、成績が上がらず「もう塾には行かない!」と泣き叫んで母親に当たったことがある。
あっさりと「じゃあ、辞めたら?」と言われたことを覚えている。
無理矢理行かされているとばかり思い込んでいた。そうかこの受験勉強は、自分が望んでやっているのか…。なんとなく、釈然としないまま、でもある程度納得をして、勉強を続けた。
中学受験は第2志望に合格した。中高一貫教育の男子校。電車で片道1時間。東京渋谷の近くだが、グランドも広く雰囲気もよい所で、自分も親も大満足の結果だった。
が、入学2日目。いきなり大泣きして家に帰った。
思春期の自分でも如実にわかるほど、同級生が異世界の人たちだった。医者の息子や有名企業の役員の息子…。彼らが使う言葉が微妙に違うのだ。その違いは胸にチクチクと突き刺さり、これから6年間それが蓄積されると思うと、思わず泣きたくなった。
なんとか気持ちをコントロールして通い続けたが、小学生の頃のリーダーシップを発揮できるような舞台はなく、クラス40人のうちのただ1人でしかなかった。「おとなしい奴」というレッテルを貼られ自分もそれに甘んじた。中学2年の時に成績順のクラスが落ちてしまった。自分としては、プレッシャーが一段軽くなったようで、解放感があった。が、それを聞いた父親が大泣きしてしまった。責められるわけでもなく、怒鳴られるわけでもなく、まるで父親が自分自身に何かを言い聞かせるように泣いていた。
ここから大学合格までの数年間。山本父子の専属コーチ生活が始まることになる。それは昭和のスポ根アニメのような日々ではない。「自分のような悔しい思いは息子にさせたくない」という至極真っ当な親心から来る日々だったように思う。結果として、山本健太は早稲田大学に進学するのだが、その数年後、仕事の第一線を退いた父も、改めて早稲田大学に一大学生として通い出すあたりが何とも微笑ましい父子である。ともかく、彼の前半生は父親と二人三脚で作られた。
父親は、いい意味で管理を始めてくれた。テストの結果で、漢字が苦手だとがわかれば「漢字検定を受けてみないか?」と提案してくれたり、通っている塾の相性が悪いとみれば、個別指導の塾を探してくれたりした。勉強だけではなく、近所の公園でトスバッティングの相手もしてくれた。
父親は高校から、さらに一歩踏み込んで関わるようになった。父母会の役員にもなり一層関わりが増えていった。模試結果をデータ化して、苦手分野をあぶり出してくることもあった。そういう父親との時間は嬉しくもあったが、時にはケンカもした。ただ友人は少なかったが、さみしい思いをしなかったのは父親のおかげだと思う。
両親は、お金のかかる趣味もなく、ただただ、自分の教育にお金と時間をかけてくれた。それなのに、肝心の大学受験。超衝撃的なほど、受からなかった。手応えはある程度あったのに、本当にびっくりするくらいどこも受からなかった。
「あれだけやったのに…。」
悲しいとか、悔しいという感情よりもまず、受け入れられなかった。1年の浪人生活を決めたが、しばらくは放心状態だった。本屋の参考書コーナーで、しばらく呆然と突っ立っていたこともあった。
我に返った時に、襲ってきた感情は「親に申し訳ない。」という強烈な想いだった。
「なんでこうなったんだろ・・・?」
と、初めて父親に相談せずに、予備校の自習室で自問自答を続けた。そこで思い出したのは小学校5年生の頃のあの思い出。「塾を辞めたいなら、辞めれば?」と言われた時の思い出。
そうなのだ、いつの間にか自分の人生なのに「両親のため」と美化しすぎてはいなかったか?
この受験は、誰のためにやっているんだ?自分自身のためではなかったか?
自分に欠けていたのは「当事者意識」。
勉強の仕方も「人気講師がこう言っているんだから、これをやっておけば大丈夫。」という風にどこか他人任せだった。そして何より自分の事なのに、父親に任せっきりになり、成績が伸びないのは父親のせいだと思っている自分はいなかったか…。
それから、自分との向き合い方、勉強との向き合い方をガラリと変えた。自習室に1人で籠り自分で作った計画を1人で淡々とこなしていった。余計な友人は1人も作らなかった。それでも、たまに両親に対するどうしようもない「申し訳なさ」が募り、自習室で独り泣いたこともあった。
2度目の大学受験の春。
無事、第一志望の早稲田大学に合格した。自分主導で考えて、それをしっかりやり抜く。そうすれば最後の最後に結果はついてきてくれた。合格発表の夜、鹿児島の親戚に電話をかけまくっている父親の姿は今でも覚えている。
実は高校時代を通して、彼が受験勉強以外に唯一打ち込んだものがある。それが「沖縄」だ。NHKの連続テレビ小説「ちゅらさん」の世界に魅了され、1泊2日の1人修学旅行を敢行している。その後も「沖縄」と付くものに、とにかく繋がりたかったらしい。まるで大好きなアイドルを追いかけるように「沖縄」自体を追いかけた時期。ただそれが人生の岐路に繋がっていくのはもう少し後の話だ。
大学生活は絵に描いたようなキャンパスライフを送った。つまりは勉学以外に精を出した。
あれほど熱心だった父親も、全く関与しなくなった。
カフェ・コールセンター・パン屋のアルバイトを経験し、サークルを2つ掛け持ちした。当時、全盛期だった「アカペラサークル」には相当ハマり、TV番組「青春アカペラ甲子園!全国ハモネプリーグ」に2回出場した。いい先輩に出会い、一気に人間関係が広がった。
就職活動も無難にこなし、金融業界に入社。父親のように新卒入社したら、ずっとそこで勤めあげる生活をイメージしていた。入社当初こそ、その部署の雰囲気に合わず辛い思いもしたが、次の部署に異動になってからは、楽しんで働くことができた。
自分としては「目標」に対して、チームが一丸となって取り組む業務は大好きだった。
他の組織に負けないよう、競争に勝つ。どこか受験勉強に似た側面もあり楽しかった。ただ勉強は独り。仕事はチームだった。そこで生まれる連帯感や達成感は、たまらなく快感だった。
ただ、大きい会社は自分の意志ではどうにもならないルールがある。次の異動部署では完全に孤立して、心も病みかけていった。そんな時、思い出したのが、高校の時に恋焦がれた「沖縄」だった。この頃から頻繁に沖縄に通うようになった。栄町のディープな夜に、どっぷり浸かり、泡盛の香りとサンシンの音色に酔いしれた。
その後も年1回は沖縄に行くようになった。観光というより、誰かに会いに行く口実を半ば無理矢理にでも作って、ただただ沖縄の空気を吸いに通った。ただ「ちゅらさん」で出会ったころと違うことが1つだけあった。ちょうど、沖縄は翁長雄志知事が誕生し、それまで東京で暮らす自分たちには届いていなかったメッセージが届くようになっていた。
沖縄に基地があることは地政学的に仕方がない。国防は国の専権事項だから沖縄の人だけが反対したって仕方がない。いつの間にかそう思い込んでいた自分の頭の裏側をガーンと殴られたような衝撃が走った。
それは、20代を終えて、30代も迎え、どこか訳知り顔に暮らすことが様になってきた自分に対して投げかけられている問いにも感じた。自分で見たわけでも聞いたわけでもないことを、知った様な顔して生きる。そんな自分の人生の主導権をあっさり他人に渡していいものか…!
翁長さんは沖縄の未来を想って、語っていたのかもしれないが、なぜか直接自分に語りかけてくれているような気になっていた。
そんな2015年。公私ともに一気に変化が起きた。約7年勤めた金融業界を退職。沖縄出身の妻と結婚。そして、大学時代のアカペラサークルの先輩が起こした会社に「参加しないか?」と誘ってもらい参加した。
自分に何ができるか?ではなく、あの時のアカペラサークルの仲間と、いつか一緒に働くのが夢だった先輩は着実にそれを実現させる道を歩んでくれていた。その熱量に感化され、当時ぐちゃぐちゃだったバックオフィス業務を一手に引き受けた。
とは言え、まだまだ小さなベンチャー企業。「自分の給与は自分で稼げ。」と取引先に常駐して働きながら、この会社のバックオフィスを整えていく。という難しいスタイルからのスタートだった。
ただこの取引先の社風というのは、聞きしに勝る刺激的な空気だった。
「この3年間でキミは何を成し遂げるの?」
という会話が当たり前に飛び交っていた。みんな自分の人生の主導権は自分が握っている人たちだった。
先輩の会社も順調に大きくなり40名規模になっていた。それに伴い、バックオフィス業務も総勢12名のフルリモートメンバーで構成されるチームに拡大していた。
金融業界を退職後、明確な目標、人生のビジョンが見えないまま、慌ただしい日々を送っていた。
受験に失敗したあの時。自問自答して学んだことは「当事者意識を持つ」ことの大切さだった。
これからの人生も「当事者意識」を持って生きるには、どうしたらいい?このまま何となく生きていってはまた自分の人生を他人に委ねてしまうのではないか?
悶々と考えた末に出した答えは、自分も「経営者」になること。そのためには働きながら通える大学院でMBAを取得することを決めた。
さらに、ただ資格としてのMBAを取るだけでは満足できなかった。大学院での課題は常に沖縄に貢献することをテーマにした論文作成や研究発表を続けた。
「沖縄にイノベーションを起こし、沖縄の未来を創造する」
沖縄生まれでもない、沖縄在住でもない自分がなぜここまで沖縄にこだわるのか?
そういう指摘にさらされながら、この想いは志へと変わっていった。

コロナ禍を経ても・・・。いや、だからこそさらに、「沖縄にビジネスで貢献したい」という想いは強くなっている。MBAも来春には取得予定だ。が、それは道の途中に過ぎない。
まずは自分自身が経営者として自立するところから始めようと思っている。
現在のチームは、コーポレート部門でありながら、採算性を求められているチームだ。守りのコストセンターではなく自ら利益を生み出すことができる攻めのコーポレートチーム。
とにかく自分の人生の主導権は、自分で握って生きていくことを決めた。
そしてこの人生の使い道は沖縄への貢献。いつの間にか当事者意識の範囲が、自分と自分の家族を越えて、「沖縄」という土地にまで拡大しているのかもしれない。途方もない挑戦かもしれないが、そう決めたあとは日々、黙々と努力を重ねるだけだ。そんな日々はもうこれまで何度もやってきた。
PROFILE

山本健太
【ITベンチャーコーポレート部門CFO・COO】
ITベンチャーにてコーポレート部門を1から立ち上げ、現在は、CFO・COOとして財務・労務を担当する約10人のメンバーを統括する。運用設計に加え、マニュアル作成・研修を含めた業務の立ち上げが得意。高校生の頃から沖縄が好きで、現在は、「沖縄をより良くするという志をもつ起業家」を一人でも多く生み出し、沖縄の社会・経済課題を解決するべく、沖縄県内でキャリアや仕事の相談受けや登壇などさまざまな活動を行っている。
-
人はいくつになっても変われるそんな物語~求められる自分と本来の自分の狭間で~
長谷川名沖
Naoki Hasegawa父親は根っからのチャレンジャー。若い時に渡米して一旗当てようというバイタリティーがあった。...
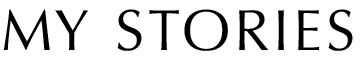

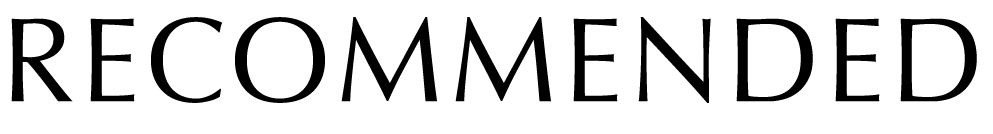


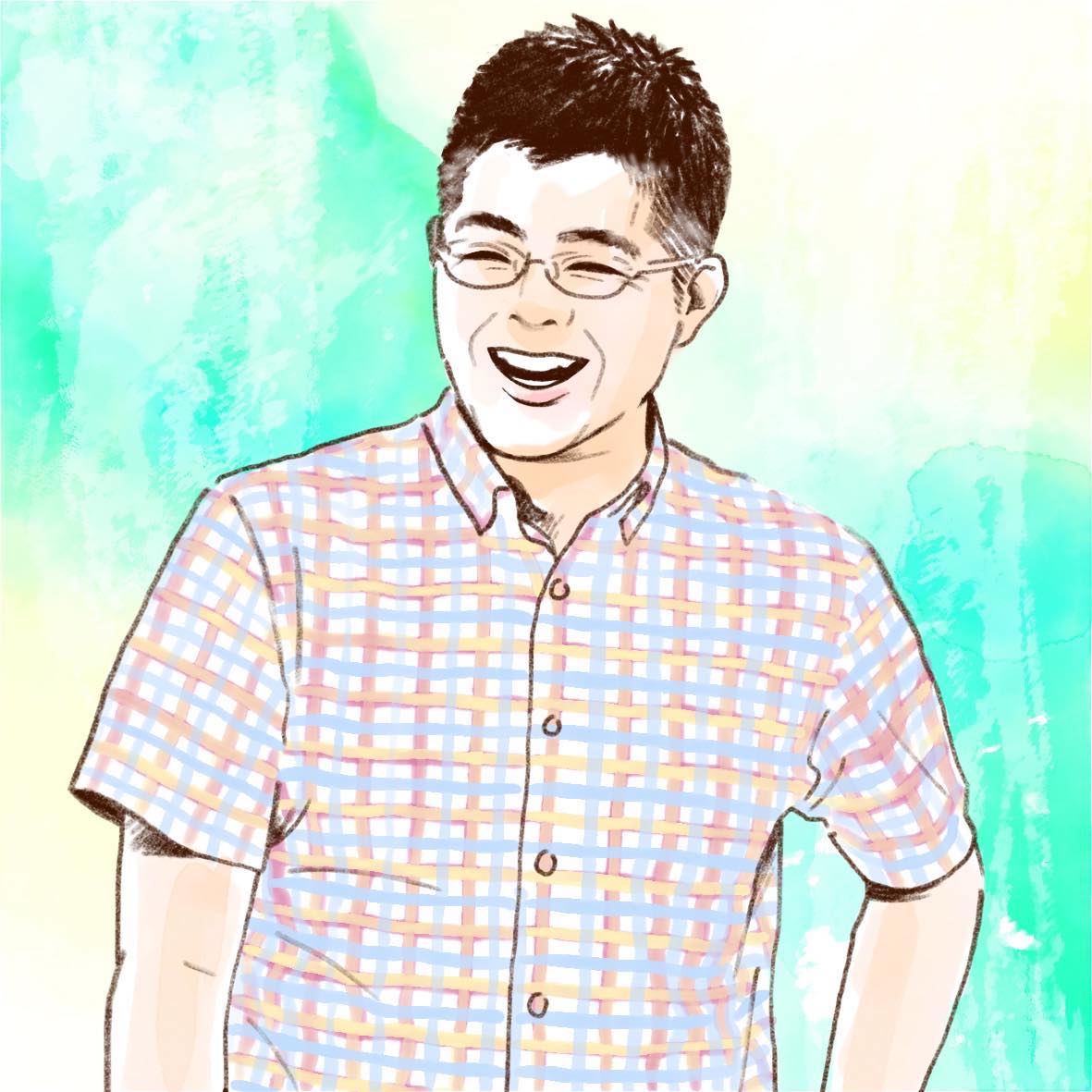
「自分らしく生きる」ことは多くの人が目指す生き方だ。だが実際は、他人のモノマネをしたり大衆の価値観に流されたりしているうちに、忘れたふりをして生きる人もまた多い。彼の口から「自分らしく生きたい。」という言葉は出てこない。それはきっと誰よりも「自分らしく生きること」に真摯に向き合っているからだと思う。これはそんな彼の物語。